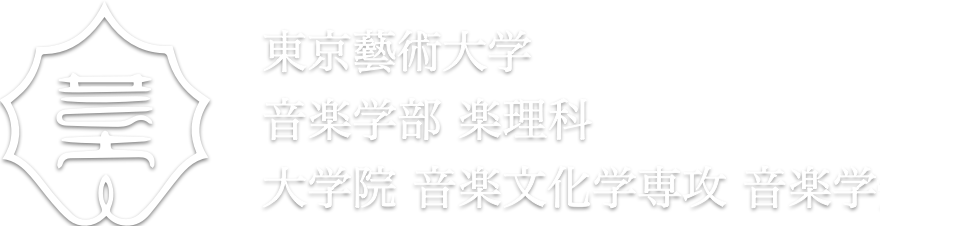博士コロキウムのお知らせ(学内開催)
11月は博士課程の学生さんのコロキウムが行われます。
時間は18:00~19:30、5-
11月04日(火)佐竹那月さん
〈題目〉
C. P. E. バッハの「自由ファンタジー」原理——
〈要旨〉
本発表の目的は、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ(
「自由ファンタジー」とは即興演奏のことであり、
本発表では、聴き手は感情的効果と音楽的「秩序 Ordnung」の両方を意識的に享受し、
「自由ファンタジー」とは即興演奏のことであり、
本発表では、聴き手は感情的効果と音楽的「秩序 Ordnung」の両方を意識的に享受し、
皆様ふるってご参加ください!
楽理科教員室