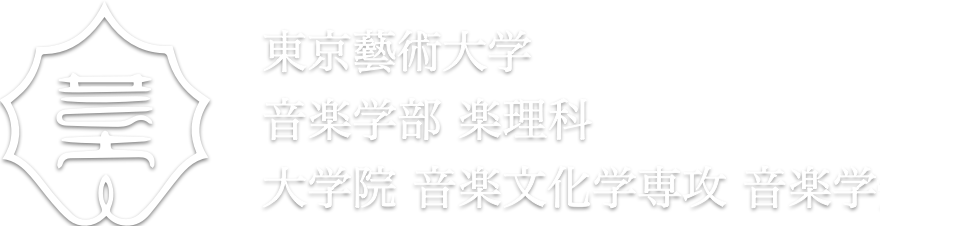教員からのメッセージ
植村幸生 教授(音楽民族学・東洋音楽史)
生きることと音楽すること
一人で二つの声をだす歌い方、鼻で吹く笛、人間の頭蓋骨で造った鼓……世界には、思わず「へぇ~」と唸ってしまいそうな驚くべき音楽の姿があります。しかし、それらをただの物珍しい、不思議な音楽と片づけてしまっては、何もわかったことになりません。なぜそのような音があり音楽があるのか。そこにどのような構造が隠されているのか。その音楽を生みだし伝えずにはいられない人たちはどのような暮らしをしているのか。そうした音楽を私たちはどのように理解できるのか。そして、人間にとって音楽とは何なのか。
こうした問いを掲げながら、人類の営みとしての音楽のありさまを、フィールドワークによって、いわば「体当たり」で解き明かそうとするのが、音楽民族学(民族音楽学)です。フィールドワークといっても、遠い異境に出かけていくばかりではありません。私たちに身近な音楽現象も、フィールドワーカーの眼と耳でとらえ直すと、自分たちの気づかない文化のかたちがみえてきたりします。
音楽民族学という窓を開いて、生きることと音楽することの関係について考えてみませんか。
福中冬子 教授(音楽美学)
一つ一つの音楽作品の背後には創作者が存在し、その創作者は同時代の社会に生きる生物であると同時に、彼・彼女以前に存在する数多の作曲者、思想家、芸術家の遺産を意識的・半意識的に模倣し、あるいは否定することで自身の創作を存在させています。また彼・彼女の創作は、好むと好まざるとに関わらず、一度彼らの手を離れれば自由な解釈作業の対象となり、それ自身の歴史を作り上げていきます。音楽を研究することは、それらすべてに目を配り、意識しながら、自分自身の解釈を探すことを意味します。みなさんも「自分の音楽」を探すことを恐れないでください。皆さんと一緒に音楽を「新しく」語ることを楽しみにしています。
沼口隆 教授(西洋音楽史)
音楽学ってなに?
「音楽学」という言葉は、日本ではまだあまり親しまれていません。でも、「物理学」とか「経済学」とか言うと、皆が何となく納得してしまうのは、少し変だとは思いませんか?多くの人にとって、「音楽」の方が「物理」や「経済」より馴染みがあるでしょうし、そのことは、子供に尋ねてみれば、より明確になるでしょう。
音楽に関わる全ての研究は、物理的な音響に関することであれ、音楽が人間心理に与える影響に関することであれ、すべて「音楽学」に含まれます。「音楽ってなんだろう?」とか「音楽についてもっと知りたい!」と思う人は、すでに音楽学への一歩を踏み出していると言っても過言ではありません。
日本で音楽学を本格的に研究できる場所の一つが東京藝術大学楽理科です。窓口は音楽ですが、そこから歴史や文化をはじめとする果てしない世界へと広がってゆきます。音楽を通して、自分の世界や未来を広げてゆきたい人を待っています。
土田牧子 准教授(日本音楽史)
日本音楽史講座では、日本で生成・展開したさまざまな音楽やその周辺の文化について教育・研究を行っています。時代的には先史時代から近現代に及び、ジャンルも多岐にわたります。主な古典音楽としては、雅楽、声明、琵琶楽、能楽、種々の三味線音楽、地歌箏曲、尺八楽などが挙げられますが、この限りではありません。近現代の日本に展開した大衆音楽、ポップカルチャーなども含まれるでしょう。
日本の音楽の特徴は、その多様性にあると私は考えています。 単に、ジャンルがたくさんあるということではなく、それぞれのジャンルが親しまれた時代や享受層によって、楽器も発声法も、教授法も譜面も、あるいは理想とされる演奏や、背景にある価値観に至るまで違いがあり、日本の音楽文化は実に多様性に満ちているのです。日本の古典音楽というと、あまり親しみがないかもしれませんが、きっと誰にとってもどこかに琴線に触れるところがあると思います。
音楽に関する個々の事象の研究は、それぞれの音楽ジャンル全体の理解へと繋がり、さらにはそれを取り巻く文化全体の探求へと限りなく拡がっていきます。小さな鍵穴からとてつもなく大きな世界が見えてくる、そんな醍醐味を一緒に味わってみませんか。