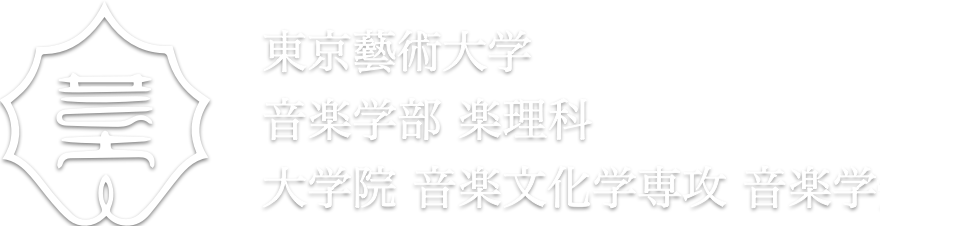博士コロキウムのお知らせ(学内開催)
11月は博士課程の学生さんのコロキウムが行われます。
時間は18:00~19:30、5-
11月18日(火)笠井恵理子さん
〈題目〉
シューマンの管弦楽法の変遷 ──ドレスデン時代に着目して──
〈要旨〉
本研究は、R.シューマン(1810-1856)の管弦楽法に着目し、その変化が顕著な彼のドレスデン時代(1844〜50年)に焦点を当て、とりわけ楽器声部の重複方法の変遷を明らかにすることを目的とする。
シューマンの管弦楽法に対しては、フェリックス・ワインガルトナーによる批判(1904) を継承した否定的な見方が多くなされ、音楽研究や演奏実践の場において軽視されてきた。アダム・カースの『管弦楽法の歴史』(1925)では、シューマンの楽器声部の組み合わせや重複方法が問題として指摘されている。またロマン派の管弦楽史を記述する中で、シューマンに言及さえしない事例も確認できる。こういった批判は、グスタフ・マーラー(1860〜1911)が、シューマンの全交響曲を再オーケストレーションしたという事実によって、一層強化されてきた。
上記の批判は主に彼の4つの交響曲が対象となっているが、最初と最後に作曲された交響曲の成立年代はおよそ10年離れており、作曲した街や初演を想定したオーケストラも異なる。また改訂された第4番の変更点が主に管弦楽法であることからも、この4つの交響曲の管弦楽法を同列に批判することには、誤った評価を誘発する恐れがある。
本研究では、シューマンの管弦楽法が変化したドレスデン時代に着目し、この時期に作曲されたオーケストラ作品を取り上げることで、ジャンル間での彼の管弦楽法の共通点や差異を明らかにする。そしてドレスデン時代以降の作風に繋がる傾向を考察する。また交響曲以外の作品も研究対象とすることで、先行研究の課題であったジャンルの偏りも解消しうる。
皆様ふるってご参加ください!
楽理科教員室