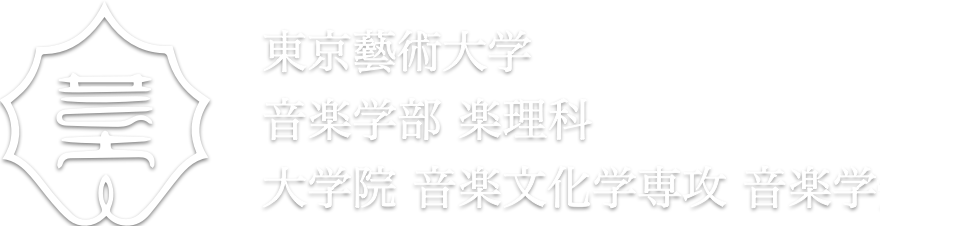第13回総合ゼミ 博士課程1年生発表
第13回総合ゼミ 博士課程1年生発表
日時:2025年11月11日(火)13:15~14:30
場所:東京藝術大学音楽学部5号館 5-408教室
発表者 ①: 牧野 友香
発表題目:宮内省楽師多忠朝の神前神楽舞の創作と普及 ──1920年代から終戦にかけての「神社音楽」概念の表出──
発表概要:
宮内省楽長を務め、雅楽の笛とヴァイオリンを奏した多忠朝(1883~1956)は、戦前から戦後にかけて多数の神前神楽舞を創作したことで知られる。彼が目指したのは新たな「神社音楽」の実現であり、日本古来の歌舞に回帰しつつも、同時代のジャズや讃歌に対抗しうる新規性をもつ演目を擁した式楽の実践であった。戦前の「神社音楽」は国体と関連づけて論じられ、国民教化の理念も負う壮大な構想だった。
これまでに、寺内直子が彼の創作曲をリスト化した上で音楽的特徴を明らかにしている。しかし、彼の「神社音楽」提唱の動機、創作神楽舞の各社への普及経過などについては、戦前の神社奏楽の主導者であるにも関わらず未だ明らかにされていない。そのため本発表では、彼の神前神楽舞の創作が「神社音楽」の実現にどのように貢献したか、同時代の雑誌から彼の活動記録を読み解いて明らかにする。
———————————-
発表者 ②:湯淺 莉留
発表題目:ジョン・フィールド(1782〜1837)のピアニズムの系譜 ──モスクワ滞在期の2人の弟子を中心に──
発表概要:
ジョン・フィールドは、アイルランド出身のピアニスト兼作曲家であり、19世紀前半にロシアを主要な拠点として活躍した人物である。本発表では、フィールドがモスクワ滞在期に指導したアレクサンドル・イヴァノヴィチ・デュビューク及びアントニ・コンツキに焦点を当て、2人がいかにして師の演奏様式を継承したのかを解明する。
デュビュークはロシア国内で後進の指導に専念し、コンツキは国内外で広範に音楽活動を展開したため、一見すると2人は対照的であるように思われる。しかしながら、彼らには、教則本と回想録の両方でフィールドに言及したという共通点がある。本発表では、これらの文献でフィールドの運指法、打鍵法、ペダリングがどのように位置づけられたのかに関して、具体例を交えて説明する。